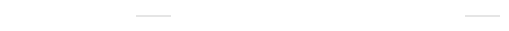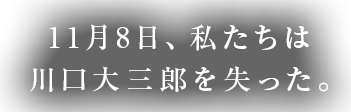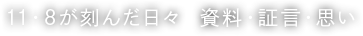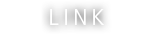40年を経た現在も「11月8日」は人生の中に重く、忘れることのできない「あの日」である。
あの日、私たちはどこで何をしていたか。授業に出ていたのだろうか、アルバイトに精を出していたのだろうか…
川口大三郎にとっても、いつものように目覚めたに違いないあの日。学校へ行き、久しぶりに体育の授業に出て「ケツが痛くてさ」とクラスメイトと言葉を交わしたいつもと変わらぬ一日。けれども、その一日に次の日は来なかった。11月8日、私たちは川口大三郎を失った。
40年の年月を経て60歳という節目を迎えた時、これまでの人生のさまざまな事柄が心に浮かび、可も不可も越えながら命を長らえたことに深い感慨を覚える。 そして思う。この人生に起こったことは、もし彼が生きていたなら川口大三郎にも起こりえたことなのだと。20歳という、まだ何も始まらない、あるいは始まりへの期待に満ちた時に断たれた彼の命、その命には、多くの可能性があったのだ。 毎年やってくる11月8日に彼を思う時、川口大三郎は私たちと共に生きている。私たちが彼の死を思うことで、彼はつねに私たちと共にいる。同じ時代を早稲田に過ごした私たちにとって、「11.8」は深く記憶に刻まれ、けっして忘れることはできない「あの日」である。
11.8以降の学内の出来事を「運動」と呼ぶとしたら、それは「なぜ川口大三郎が殺されなければいけなかったのか」という2Jの問いかけに始まった。
川口大三郎は狭山事件の集会などに顔を出してはいたが、どこの党派にも属していなかった。にもかかわらず自治会は、川口大三郎を反革マルと決めつけ、拉致監禁して、暴行によって死に至らしめた。さらに破廉恥なことに、自分たちの行為を正当化する発言を文学部構内で声高に繰り返そうとした。そのあまりの理不尽さに、抑えきれない怒りが2Jを突き動かし「2J行動委員会」として結束し、川口大三郎の死の真相を明らかにする活動へと導いた。何ができるか、何をすべきか2Jが討論を重ねる一方で、一文校内では1Jがマイクで学友に呼びかけ、2Tの名前で「自治会糾弾」の立て看が立った。呼びかけに集まる学生の輪は日に日に大きくなり、殺害の首謀者である自治会とそれを容認した大学当局を糾弾する集会が開かれるようになった。そして、ついには学部を越えて、全学的な運動へと発展したのだった。
それが私たちの「11.8」の始まりだった。
私たちがやろうとしたことは何だったのか、それはどこへ向かおうとしていたのか。「11.8」はまだ終わっていない。
川口大三郎の死を機に立ち上がった学友よ、今ふたたび「11.8」を語らないか。そしてお互いの言葉に耳を傾けようではないか。
共に語る時間を持つことで、自分の生きた人生の中で見失った何かを見つけ出せるかもしれない。あの日どこにいて、何をしていたか、あの日から、どんな道をたどって生きてきたのか…。一人ひとりの足跡をたどることで、より鮮明な「11.8」を残そうではないか。
川口大三郎と同じ時代を生きた一人として、あなたの言葉を発してほしい。
そして、その言葉を記録することで、私たちの心の中で共に40数年を生きた川口大三郎へのオマージュとしようではないか。